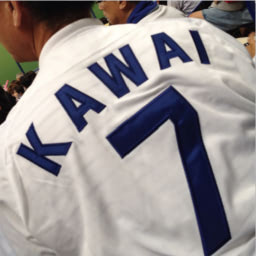概要
キヅキランドの構築をお手伝いしました。 キヅキランドについては、キヅキランド通信に詳しく書いてありますので、そちらをご覧下さい。
今回、かなり長いスパンで開発に携わらせて貰う機会を頂きました。
最初にお話を頂いたのは、2020年の夏~秋くらいの時期だったと記憶しています。そこから、どういう事をしたいのかという事を伺い、Web で何をしたらその目的のために有効なのか、試行錯誤の日々が始まりました。
こんな長期に渡る開発は普段は余り経験しません。個人的には、エンドクライアントである稲盛財団の皆様がたから見受けられる、良い物を作る、その作ったものを通じて、社会に貢献するという使命感のような思いについて、意気に感じるところがありましたし、ご担当の皆様や一緒に制作に当たった制作チームの中にある熱気に貢献しなくてはと心に期するところもありました。
プロトタイプをああでもないこうでもないと色々作ってみては、多様なバックグラウンドを持った大勢のチームの皆の中でフィードバックを受け、また次のプロトタイプを作ってみて…と繰り返されていくプロセスの中から、「動画に書き込みをする体験」こそが Web というメディアが可能にする、今回の鍵になるのではないかというキヅキが産まれました。
ここまでで、おそらく半年以上が経っていました。プロトタイプは今回少し欲張って、体験以上のところまで視野を広げ、Web サービスとして自走可能になるくらいの運用を目指した大枠がある程度見えるくらいまで膨らんでいました。ですが、今回のプロダクトには大きな目標となるリリース時期がありました。夏です。
夏。今回のサービスがターゲットとする小学生達が、夏休みを迎える大切な時期です。ここには、何らかの形でリリースをして、実際に使ってもらいたい。そのタイミングを逃したくない。でも、膨らんでしまったプロトタイプの開発が押して、リリースを目指す動きに入ったのはもう春になっていました。時間の余裕はありません。
そこで最初は Web サービスとして自走するのではなく、今回リリースする Web サイトを道具に使った、ワークショップを行うのはどうですかというご提案を行いました。幸い、エンドクライアントの稲盛財団さんは、夏に子供達を集めてイベントを実際に行うという経験を持っておられました。そもそもコロナ禍の中、そのイベントが行えないからこそこの企画が始まったのです。また、僕らと一緒に制作をしていたプロダクトチームの中にも、そういった Web イベントでのコミュニケーションに長けた人材がおられました。幸運な偶然か、それとも必然か。夏休みは、そういった皆様のお力もお借りして、リアルタイムでコミュニケーションを取りながら、実際に子供達に使ってもらおう、という事になりました。当初思い描いていた Web サービスとして自走し出す形とは違いましたが、これは、振り返ってみると、大変良いピボットでした。ご理解を頂き、応援して頂いた皆様に感謝したいと思います。
まず第一に、Web サービスにするなら必要な立て付けの多くが省略できました。アカウントを登録や削除を行えるようにすること、そもそもこのサイトは何でどうやって使うのかというのをWebサイト上だけで説明すること、サービスを運用するための日々の作業のために必要な管理機能。どれも重要ですが、体験の核である「動画に書き込みをする体験」そのものからは、少し離れています。核となるものを実現する手段ではありますが、実装の手間も相応にかかるものを削ぎ落し、リアルタイムのコミュニケーションでフォローする、という事でそれらに代え、より核となる体験にフォーカスした開発が行えました。
また、判断し、設計しなければいけない数多くの事も、ワークショップのそれぞれの回のイベントの中に閉じることで、この段階では心配せずに済みました。Web サービスとして公開されたら、ユーザによって投稿されたデータをどういう範囲で公開するか、各アカウントにSNS的なフレンド機能をつけるべきなのか。いいね!みたいな機能をつけた時に承認欲求が暴走して、結果として目立ったもん勝ちな空気になり本来の意図にそぐわない投稿を助長したりはしないか、などという悩みは少しプロダクトチームの中の話題に上がりましたが、これらも、大人の目の届くワークショップの範囲の中でなら問題にする必要がありません。
何より、子供達の反応が、ダイレクトに返ってきました。これは本当に大事なことでした。開発中に自分達が作っていたものは、まだ、世の中に試みられていないものです。本当に子供達が受け入れてくれるのかどうか不安は実際にワークショップのイベントを行い、実際にそこに書いてくれる子供達の反応を見ている内に雲散霧消しました。子供達は本当に楽しそうだったのです!とてもうれしかったし、自分達の仮説の中で核とした体験が、ターゲットの心を射貫けた事に感動しました。
諸々の苦心はありましたが、まずは体験として、充分強度のある核を作れました。引き続きこのプロジェクトは進んでいきます。今度は、今回スキップした部分を新たな課題とし、Web サービスとして独り立ちしていくように育てていかねばなりません。ワークショップ版で得た手応えを活かし、より良い形でサービスとしてリリースできるようにがんばります。